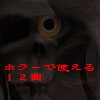同人ゲームやフリーゲームはもちろん、ゲームデザイナーを目指す人、これからゲームを作りたい人、今もゲームを作っているがなかなかうまくいかない人向けの、ゲーム開発に関するブログ。
2026/01/07 (Wed)
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2016/02/24 (Wed)
PLの突飛な行動を防ぐために構造のズレを無くす
RPGにおけるPLとGMの責任について、ロールプレイが指す意味とGMの存在において、PLは自分の行動について責任を持とうと言う旨の内容が掲載されましたが、正直な感想を述べると、セッションの失敗の要因をPLに押し付けている だけではないかなと感じました。申し訳ないのですが、例として挙げられているPLの行動はGM側で防げますし、PLの行動の結果として挙げられた対処はただの腹いせによる報復です。ただただ準備不足で下手なGMの例になっているなと感じました。
以下、おかしいなと思った点。
構造のズレ
「町外れにある館にいる吸血鬼を倒して欲しい」というセッションで、館の中に入らず外から火をつけて燃やす。という行動をした
そもそもこの行動を問題視する事自体が間違いです。真っ先に目立つ点として、GMがPLにやらせたかった事と、NPCからPCへの依頼にズレがあり、シナリオの作りそのものに構造のズレがあります。
- 構造のズレ
- NPCからPCへの依頼
- 町外れにある館にいる吸血鬼を倒して欲しいという
- GMがPLにやらせたかった事
- 吸血鬼との戦闘と館の探索
- NPCからPCへの依頼
依頼内容にはPLにやらせたいことの半分も含まれておらず、館を残せとは一切言われていません。PC側からすれば自分たちの体力、戦力の温存のため、最大の結果を出そうとして館に火をつけると言うのは極めて合理的な判断と言えます。
村に火が燃え移っただけではなく周囲の森にまで広がり、PC達は命からがら逃げ出すことしかできなかった。それだけではなく国中から指名手配される事になった。
その結果として指名手配とするのは、GMがPLにやらせたかったことをしてくれなかった腹いせによる制裁です。この結果は良くない。本当に良くない。
放置された家屋であればともかく、吸血鬼とはいえ人が住む家である以上、館の周辺にはある程度の手が入れられていますし、森の中にあるとしても、 周囲の木々とは一定以上のスペースがあると考えてしかるべきです。これは、家からの失火で周囲が火事になるのを防ぐだけではなく、外部から何らかの原因で火が出た際、我が家に燃え移らないようにするためのスペースでもあります。また、舞台設定で「町外れにある館」とわざわざ指定しており、物理的に町や村から距離がある家屋の失火が燃え移るというのもおかしな話だし、周囲の森にまで広がるというのも、よほど乾燥していて風が強い日でもない限りありえません。
例えば、クリティカルで成功したとか、ファンブルで成功したとかのギミックで、やりすぎてそうなったって言うのならまだ解ります。それなら PL側も納得がいくでしょう。ただ、例として挙げられている処理内容は普通に成功したものなので、そこまでの処理をするのはマスタリングに問題があると言わざるを得ません。
指名手配と言っても、それだけ大規模な火災であれば犯人探しも非常に難しいでしょう。それなのにPCを名指しにしているのはGMが犯人を知っているからです。PLとPCの知識に差があるのと同様にGMと世界の知識には差があって当然です。なので、これはGMの腹いせであると断言できるのです。
指名手配と言っても、それだけ大規模な火災であれば犯人探しも非常に難しいでしょう。それなのにPCを名指しにしているのはGMが犯人を知っているからです。PLとPCの知識に差があるのと同様にGMと世界の知識には差があって当然です。なので、これはGMの腹いせであると断言できるのです。
この状況になった結果の責任は火をつけたPL達にはありません。何度も説明した通り、GMによる意図した行動をとらなかったPLに対する腹いせであり、腹いせである以上、この結果の責任はGMにあります。回避するにはどうしたらよかったのか? GMとしてはそちらを考えた方が建設的でしょう。
問題点は、GMが意図した行動をPLにとらせられなかった、誘導できなかった、上手く伝えられなかったという点です。つまり、シナリオの構造の問題なので、まずはここを見直してみましょう。
改善案
構造のズレで指摘した通り、NPCからPCへの依頼とGMがPLにやらせたかった内容に食い違いが見られます。という事は、NPCからPCへの依頼内容を修正すればこの問題は解決します。
思いつく方法としては以下の物が挙げられます。
- 吸血鬼の倒し方を指定する
- 館内のあるものの探索を依頼し、そこに番人として吸血鬼を出す
あくまでも例に過ぎませんが、この他にも色々あるのではないかと思います。
もう一度整理しましょう。GMがPLにやらせたかった事は以下の二点です。
- 吸血鬼との戦闘
- 館の探索
それに対してPCに依頼された内容は以下です。
- 吸血鬼の討伐
表にしてみると解りやすいでしょう。
| PLにやらせたかった事 | 吸血鬼との戦闘 | 館の探索 |
| PCへの依頼 | 吸血鬼の討伐 |
戦闘と討伐に食い違いがありますし、館の探索はマストではありません。よって、それぞれにしなければならない理由を付与してやれば、もう少し違った結果になるはずです。
- 吸血鬼と至近距離で戦わなければならない理由
- 館を探索しなければならない理由
これら二つをしっかりと用意して上記の表を下のように修正してやれば、プレイヤーが館に火をつけるという行動はかなりの確率で防げます。
| PLにやらせたかった事 | 吸血鬼との戦闘 | 館の探索 |
| PCへの依頼 | 吸血鬼と戦闘しなければならない | 館を探索しなければならない |
GM側のシナリオの練りこみミスをPLに責任転換するのは良くありません。TRPGのセッションの失敗をPLがお客さん根性だからとか、PLも責任を取るべきと言うような論は少なからず散見されますが、PLに責任を擦り付けていると面白いGMにはなれないし、TRPGも面白くなりません。 PLが意味の分からない行動をとった場合、GM側は十中八九、シナリオの構造に問題があると思った方がいいでしょう。
結局、そのセッションの面白さはGMが用意したもの以上にはなりません。
つまらなかった、PLが思った通りの行動をしなかったとぼやく前に、GMは本当にやれることをやったのか、という点を見直すべきではないかと感じています。
依頼などに垣間見る甘さ
上記で言えば依頼を受ける前提でお話を組んでいる所にそもそもの問題があります。 依頼そのものは断れます。そして、途中で放棄もできます。なので、前提からして構造が甘いと言わざるを得ません。依頼の形式にするのであれば、断れず途中放棄も難しい状況にしないと、PLは途中で放棄することも断ることもできます。
吸血鬼を倒すクエストを例にしてみましょう。例えば以下のような内容であればどうでしょう?
PLを含め全員がすでに吸血鬼の下僕と化しているが、吸血鬼の生首を館の地下の祭壇に掲げればこの呪いを解くことが出来る。しかしそこは厳重に封印されており、ラスボスの始祖が存在する。下僕は毎日毎日使い捨ての奴隷とされているため、留まるのは危険で、かつ、食事は人間の生血で、補充は館内でなければ難しい。舞台設定を用意しておけば断りにくくなります。あとはPLを適当に配置すればなんとでもなるでしょう。使い捨ての 奴隷にしておくか、生血の食料にしておくか、あるいは逆に吸血鬼の側にしておくか。ここから先はGM次第ですが、ただ依頼を受けるよりもよっぽど楽しくなります。
構造の甘さは処理の甘さにも出ています。
PL「敵は?」
GM「わからないよ」
PL「えーっと調べる?」
GM「んーどうやって?」
自分の家がゴウゴウと燃えている状況で外を見ないで、焼け死ぬまでその場に留まるというのは、固定されたロボットぐらいのものです。この場合、まず敵は 外を確認するので、火をつけた本人にはマイナス修正をつけ、PC全員に隠密判定をするのがオーソドックスな処理です。一人でも見つかったら即戦闘に入ります。誰も見つからない場合は消火しにくるため1ターン不意打ちの機会を得られます。以後の戦闘は、毎ターン増援がある状態で、館内全ての敵との戦闘、と自分ならばそうします。館内からの射撃があるので、敵側にややボーナスを用意した状況で進めるでしょう。増援に関しては焼死や逃亡などで一定の数が減っている物として処理します。
非常に失礼な感想ではありますが、火をつけたPLに対して「わからないよ」と即答してしまうのは、物語への反映を拒みコミュニケーションの断絶をGM側から行っています。この程度の変更を臨機応変に行うのは別に離れ業でもなんでもありません。そもそも突拍子の無い行動ではないし、想定していなくとも敵側の想像ができれば対応は難しくありません。
考えつかない場合は、PLに想定外だったので一緒にちょっと考えようと提案し、敵側だったらどうするかを質問するのも一つの手ではないでしょうか。手に負えない場合、頭を下げて時間を巻き戻すのもいいでしょう。それがコミュニケーションという物ではないでしょうか?
モンスターをどうしても倒したくない非殺生キャラだとか、女の子を見ると殺したくなるシリアルキラーだとか、宝箱を見るととりあえず開けて罠は全部発動させるトリックスターだとか。そういった突飛な行動をするPL達
これらについても、突飛な行動といってもちょっと想定外な程度でしかありません。突飛な行動と決めつける事で、「想定と違うと許可出来ず、物語への反映を拒む」ための、言い訳に使っているだけに過ぎません。モンスターをどうしても倒したくない非殺生キャラをやりたいのならやらせてやればいいんです。
例えばオープニングで切りかかられる戦闘からスタートし、設定を守るプレイヤーならそこで反撃せず瀕死になるだろうから、NPCに代わりにモンスターを倒させ、そのNPCに何故倒さないのかを聞かせてやればいいんです。PLは設定を話したいから、そういう設定をつけています。話を聞いた後にじゃあこれで守っ てくれと、シールドを渡すなどをしてやるとそのNPCの印象が良くなるでしょう。後はシナリオ内で、そのPCがモンスターを倒さなければ、オープニングで助けてくれたNPCが死ぬ。というシチュエーションを用意してやれば、きっと面白くなります。
女の子を見ると殺したくなるシリアルキラーも、オープニングにうまく取り込むことは出来ます。
もし、手に余るようならば、「悪いけどその設定、僕には扱いきれないんで下げてもらいたい」と頭を下げればいいんです。取り入れられないからコミュニケーション能力が無いわけではありません。思いつかない時は思いつきません。できないと思ったことを素直に認めて、それを相手に伝えて下げてもらうのもコミュニケーションです。TPRGはコミュニケーションのゲームで、GMは神様ではないのですから、悪いけど手に負えないから無理と頭を下げる方法がありますし、逆に突飛だからと片付けてしまうのはGMが神様であることを押し付け、コミュニケーションの断絶をも意味しています。よって非常によろしくありません。
その行動を面白いと思えば突飛な行動ではないし、その行動に理解を示さなければ突飛な行動になります。突飛かどうかの判断基準は、ただ単にGM側の心象に過ぎないのです。
PLの心理コントロール
PLがやるべきことを見失っている場合、突飛な行動を取る傾向が強くなります。要は、ヒマだからそういう事をするようになります。
これをやらないとやばい事になる。そういう心理状態に持っていけていれば、たとえシリアルキラーの設定をもったPCでも、シナリオの目的とキャラ設定を上手く組み合わせてくれます。卓についている以上、非協力的ではないのです。
シナリオの解決とは、主に舞台となる場所で特定の組織が損をしており、それを回避しようとして第三者に委ねる形で行われます。この第三者がPCであり、依頼という形でお願いすることが多いと思いますが、第三者であるがゆえにPCには損がありません。損が無いので危機感を持てません。 だったら、第三者ではなく当事者にする事が近道です。
よって、セッションをより上手く動かすコツは、PCに回復できるが致命的な損を与えてやる事です。そして、その回復方法を明示してやりましょう。そうすればプレイヤーに明確な目的とモチベーションが芽生えます。往々にして、突飛な行動を行うプレイヤーというものは、こういった明確な目的を与え られていないPCをプレイしています。これはGM側の心理コントロールミス、誘導ミスに依るところが大きな要因を占めています。
相手の心理を誘導するために大胆に損を植えつけてやりましょう。「こういう状況で、これをしないと、キャラロストする」と明示してやると人は損に動かされるので回避しようと模索を始めます。そして、プレイヤーの賢さを信じましょう。プレイヤーはGMが思う以上に賢くバカな存在です。どんな大胆に損を植えつけても、キャラ設定を否定しない限り自キャラとの整合性は見出してくれます。なのでまずは信じましょう。プレイヤーを。
相手の心理を誘導するために大胆に損を植えつけてやりましょう。「こういう状況で、これをしないと、キャラロストする」と明示してやると人は損に動かされるので回避しようと模索を始めます。そして、プレイヤーの賢さを信じましょう。プレイヤーはGMが思う以上に賢くバカな存在です。どんな大胆に損を植えつけても、キャラ設定を否定しない限り自キャラとの整合性は見出してくれます。なのでまずは信じましょう。プレイヤーを。
PR
プロフィール
HN:
色々ありすぎでどれを名乗ろうか
Webサイト:
性別:
男性
自己紹介:
素材屋GY.Materialsを運営。
TRPGや同人ゲームなどを制作。イベントプロデュース等。
TRPGや同人ゲームなどを制作。イベントプロデュース等。
カテゴリー
最新記事
(01/23)
(03/14)
(11/01)
(09/01)
(08/23)
P R