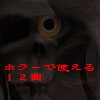同人ゲームやフリーゲームはもちろん、ゲームデザイナーを目指す人、これからゲームを作りたい人、今もゲームを作っているがなかなかうまくいかない人向けの、ゲーム開発に関するブログ。
2026/02/15 (Sun)
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2016/03/13 (Sun)
表現者よ、生意気であれ
ご存知の方いらっしゃると思いますが、自分は元オペラマネージャーです。その業務中こんなことがありました。
その日の業務は、あるオペラの公演のチラシを作る事でした。リテイクを出され、不本意ながらデザインを変更させられたのです。研修生の公演であったのもあり、どこで行われる公演で、チケット代がいくらなのかと言う部分が解るようにしたデザインで、内部での評価は高かったのですが、担当している先生のお気には召しませんでした。
変更点は以下の物でした。
・出演者の名前を大きくする。
・和風の演目、洋風の演目それぞれで出演者のフォントを統一。
・会場に関する情報はもっと小さく。
……誰のためのチラシなのか、と言う部分で大きな食い違いがありました。先生は出演者のため、自分は来場されるお客さんのためをそれぞれ意識していました。とはいえ歯向かう事もできないため、渋々新しいデザインを送信しました。すると次は出演者の文字をもっと大きくしろとの事でした。即座に修正しなおし、FAXを送り、「いいじゃないこれ、これで行きましょう」と了承を得ます。
翌日。
朝一の電話はお怒りの電話でした。
「あなた、なんで出演者の字がこんなに大きいの!」
お前がそないせぇって言ったんちゃうんかいと半ギレになりつつ、すみません、すぐに直しますんで、と言って、昨日送った修正前の物をFAXで送信したところ、返ってきた返事は「いいじゃないこれ」でした。
この当時は一介の社員に過ぎなかったので致し方ない部分ではありますが、出来上がったチラシは自己顕示欲の塊の醜悪な物で、駄作と言わざるを得ない物でした。自分の力及ばず駄作になったのであればともかく、第三者の自己顕示欲で駄作に落とされた感覚で、正直作品に泥を塗られた気持ちでいっぱいでした。
この一連の流れはオペラがなぜ廃れたかの理由を良く表している作成過程と言えます。つまり、自分たちのための歌、自分たちのためのチラシ、自分たちのための公演が目的だから廃れたのです。
怒られたりクレームが来る事に対して恐怖を抱いていた、と言うのも正直あります。逆らいようのない上下関係、そして自分の失態は他の人にも波及するという強迫観念のようなものもありました。それゆえに先生の言う事を聞き自分の作品を曲げてしまいましたが、これがもし、どこかで対等な立場であれば、強く反論していたと思います。それで仕事が無くなっても構わない、と言う気持ちでここでナマイキな事を言うべきなのです。お互いのために。
オペラが腐ったのはナマイキな人がおらず、先生を持ち上げ、持ち上げる生徒だけを優遇し、そして何よりも高すぎるチケットノルマという障害のせいで、歌の実力よりも金持ちかどうかで主役が決まってしまう環境が主な要因に挙げられます。生徒側も先生を選ぶ際、実力よりも主役をしたことが有るという肩書で選んでしまいます。ほとんどの人がなぁなぁでやっていました。結果として残ったのは、娯楽は元来商売であると言う当たり前の部分を忘れた人たちです。
(主役級は300万にやや満たないぐらいのノルマで、構造としておかしいと言わざるを得ません)
研修生の段階ですら、チケット代を支払い、さらには往復の時間と交通費を使わせた来場者の側を向いていません。チラシ一つとっても、客席よりも自分たちを優先するその姿勢が、恥ずかしいと思わないのかと、ナマイキをいってぶつからなければならなかったのです。マネージャーだったんですから。マネジメントする対象が儲からないと、マネジメント業は儲からないはずなんです。
生意気と失礼は違います。言葉遣いなどによる失礼は避けるに越したことはありません。だけれども、生意気さは真剣に取り組むからこそ生まれてくるものです。特に表現者はそのナマイキさをもって、共演者、共同で作業する人、そして観客と世の中に喧嘩を売るのが仕事なのですから、このナマイキを失ってはいけません。
これを言ったら失礼かな? と思われそうなことは、表現や言い方を探したり、言わないように心がけるのは正しいと思います。しかし、これ言ったら生意気だと思われるかな? と迷った事は言いましょう。きっと思っていたよりもいい結果になるはずです。
その日の業務は、あるオペラの公演のチラシを作る事でした。リテイクを出され、不本意ながらデザインを変更させられたのです。研修生の公演であったのもあり、どこで行われる公演で、チケット代がいくらなのかと言う部分が解るようにしたデザインで、内部での評価は高かったのですが、担当している先生のお気には召しませんでした。
変更点は以下の物でした。
・出演者の名前を大きくする。
・和風の演目、洋風の演目それぞれで出演者のフォントを統一。
・会場に関する情報はもっと小さく。
……誰のためのチラシなのか、と言う部分で大きな食い違いがありました。先生は出演者のため、自分は来場されるお客さんのためをそれぞれ意識していました。とはいえ歯向かう事もできないため、渋々新しいデザインを送信しました。すると次は出演者の文字をもっと大きくしろとの事でした。即座に修正しなおし、FAXを送り、「いいじゃないこれ、これで行きましょう」と了承を得ます。
翌日。
朝一の電話はお怒りの電話でした。
「あなた、なんで出演者の字がこんなに大きいの!」
お前がそないせぇって言ったんちゃうんかいと半ギレになりつつ、すみません、すぐに直しますんで、と言って、昨日送った修正前の物をFAXで送信したところ、返ってきた返事は「いいじゃないこれ」でした。
この当時は一介の社員に過ぎなかったので致し方ない部分ではありますが、出来上がったチラシは自己顕示欲の塊の醜悪な物で、駄作と言わざるを得ない物でした。自分の力及ばず駄作になったのであればともかく、第三者の自己顕示欲で駄作に落とされた感覚で、正直作品に泥を塗られた気持ちでいっぱいでした。
この一連の流れはオペラがなぜ廃れたかの理由を良く表している作成過程と言えます。つまり、自分たちのための歌、自分たちのためのチラシ、自分たちのための公演が目的だから廃れたのです。
怒られたりクレームが来る事に対して恐怖を抱いていた、と言うのも正直あります。逆らいようのない上下関係、そして自分の失態は他の人にも波及するという強迫観念のようなものもありました。それゆえに先生の言う事を聞き自分の作品を曲げてしまいましたが、これがもし、どこかで対等な立場であれば、強く反論していたと思います。それで仕事が無くなっても構わない、と言う気持ちでここでナマイキな事を言うべきなのです。お互いのために。
オペラが腐ったのはナマイキな人がおらず、先生を持ち上げ、持ち上げる生徒だけを優遇し、そして何よりも高すぎるチケットノルマという障害のせいで、歌の実力よりも金持ちかどうかで主役が決まってしまう環境が主な要因に挙げられます。生徒側も先生を選ぶ際、実力よりも主役をしたことが有るという肩書で選んでしまいます。ほとんどの人がなぁなぁでやっていました。結果として残ったのは、娯楽は元来商売であると言う当たり前の部分を忘れた人たちです。
(主役級は300万にやや満たないぐらいのノルマで、構造としておかしいと言わざるを得ません)
研修生の段階ですら、チケット代を支払い、さらには往復の時間と交通費を使わせた来場者の側を向いていません。チラシ一つとっても、客席よりも自分たちを優先するその姿勢が、恥ずかしいと思わないのかと、ナマイキをいってぶつからなければならなかったのです。マネージャーだったんですから。マネジメントする対象が儲からないと、マネジメント業は儲からないはずなんです。
生意気と失礼は違います。言葉遣いなどによる失礼は避けるに越したことはありません。だけれども、生意気さは真剣に取り組むからこそ生まれてくるものです。特に表現者はそのナマイキさをもって、共演者、共同で作業する人、そして観客と世の中に喧嘩を売るのが仕事なのですから、このナマイキを失ってはいけません。
これを言ったら失礼かな? と思われそうなことは、表現や言い方を探したり、言わないように心がけるのは正しいと思います。しかし、これ言ったら生意気だと思われるかな? と迷った事は言いましょう。きっと思っていたよりもいい結果になるはずです。
PR
プロフィール
HN:
色々ありすぎでどれを名乗ろうか
Webサイト:
性別:
男性
自己紹介:
素材屋GY.Materialsを運営。
TRPGや同人ゲームなどを制作。イベントプロデュース等。
TRPGや同人ゲームなどを制作。イベントプロデュース等。
カテゴリー
最新記事
(01/23)
(03/14)
(11/01)
(09/01)
(08/23)
P R